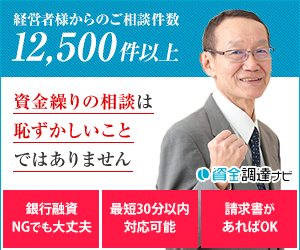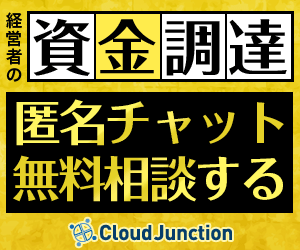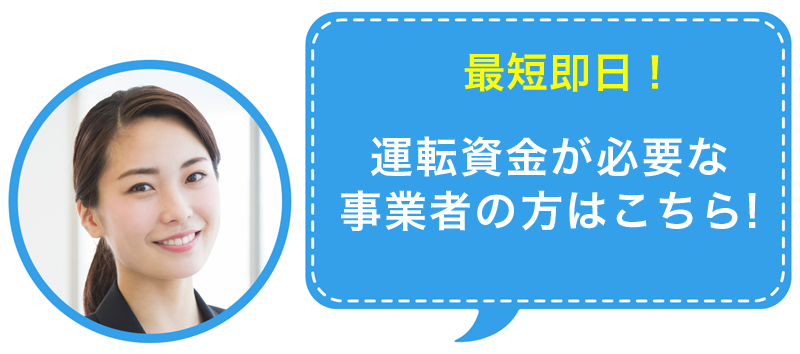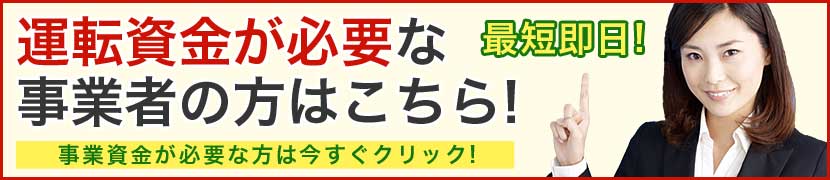モニタリングとは、観測や測定を行う手法のことで、特定の状態の監視や観測を行うことです。モニタリングシステムとは、コンピュータ制御などにより、自動で行うモニタリングで、最近ではこうしたシステムを導入する金融機関も増えています。
では何の為に、こうしたシステムを導入するのでしょうか。
もちろん、コスト的にも人海戦術で行うより、コンピュータによる自動システムの方が、パフォーマンス性にも優れています。現在、2020年度の債権法の改正により、売掛債権評価モニタリングシステムが注目されるようになってきました。
金融モニタリング基本方針
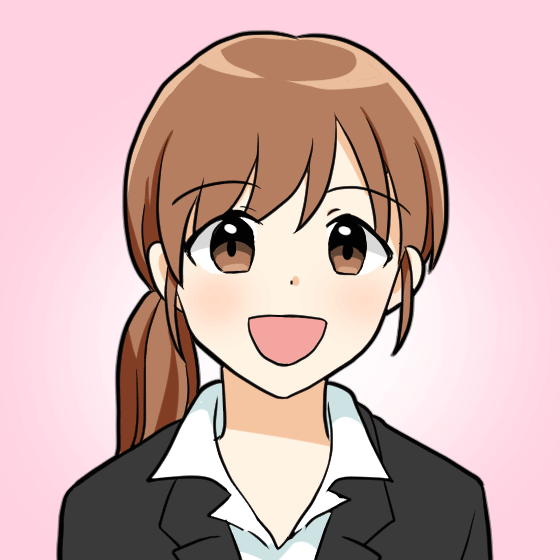
コンピューターが発達した今の時代を象徴しているわね。
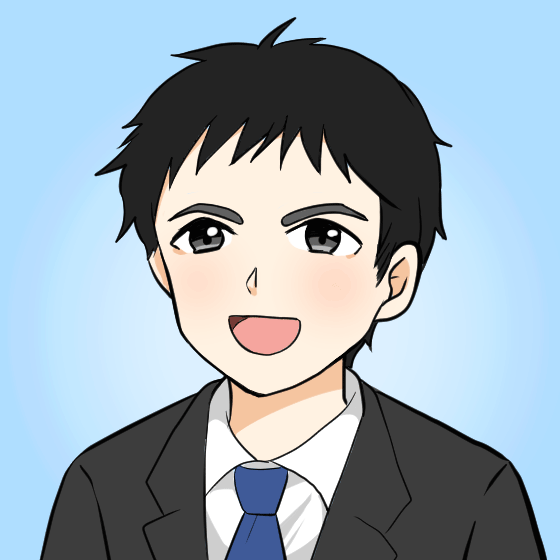
実際にこれまで人為的に行わなければならなかった作業はコンピューターになり替わっているよね。
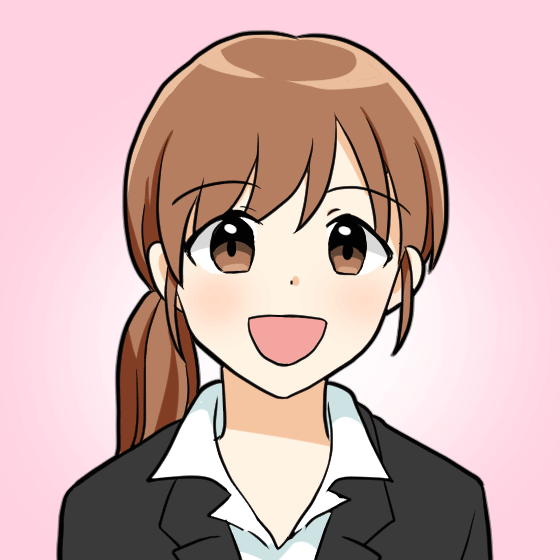
便利になったのはわかるんだけど、これもファクタリングに関係があるの ?
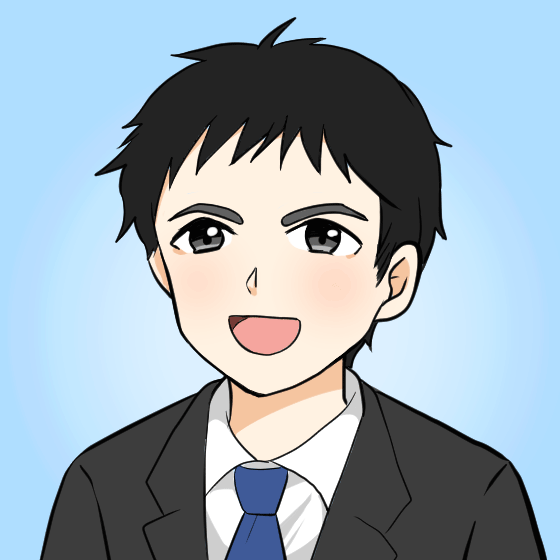
大いにあるね。そこで今回はファクタリング業界で活用され始めている売掛債権評価モニタリングシステムについて解説していこうと思う。
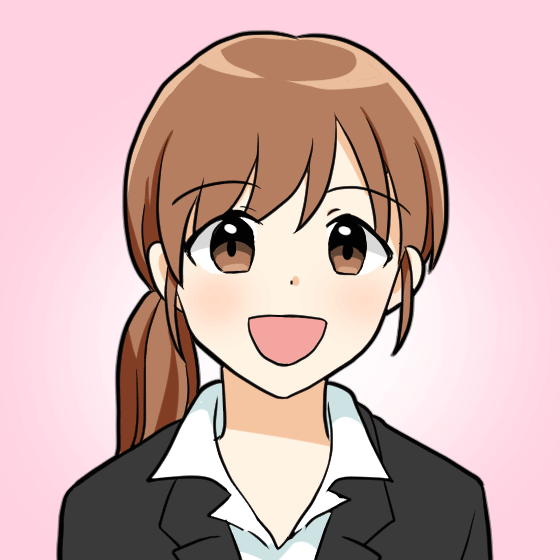
よろしくお願いします ! 先輩!
金融モニタリング基本方針とは、金融庁がこれまでの検査基本方針に代わり、2013年に金融モニタリング基本方針として公開したものです。この背景には、デフレが長引く日本国内において、デフレ脱却に向けた好循環の実現推進を図る為です。
また同様に、環境の変化に対し、金融システム及び、金融機関の健全性を維持する為の対応を重視する事から、監督及び検査の基本的な考え方を示したものです。さらに翌年の2014年度には、監督局と検査局とのより一層の連携を図る為、重点施策として公開されることになったわけです。
これは、当然の事ながら、景気策の一環で行われているものですが、金融の好循環を実現する為、顧客のニーズを第一に考えられたものです。つまり、真に顧客の利益になる金融商品と、これに関連するサービスを提供しているか検証することが大前提です。
さらに、金融仲介機能の発揮にあたっては、借り手企業側の事業内容及び、成長可能性を適切に評価した上、融資や助言を行う取り組みを行っているか検証することとしています。また、リスクの状況を、将来を見据えた分析態勢を強化すると共に、各国の金融や行政などとの連携態勢も強化するとしています。
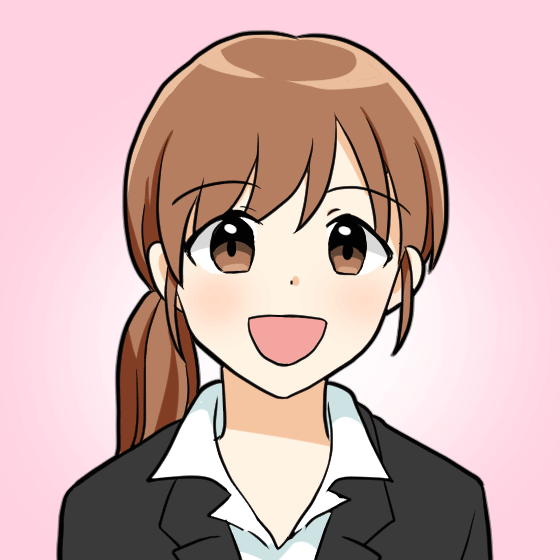
要するに、資金調達活動を行いやすくする為、という事かしら?
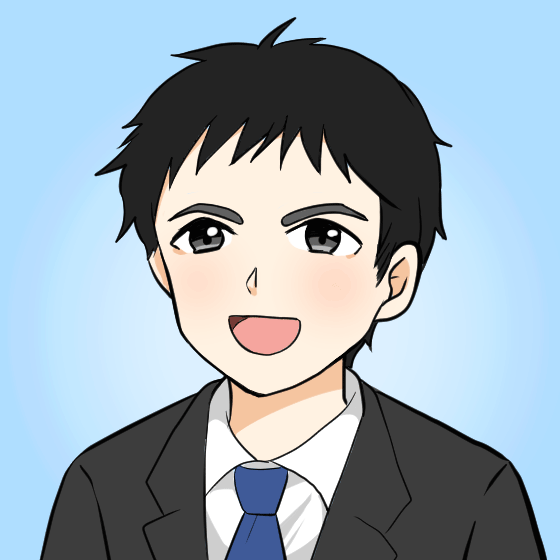
関連するのは金融サービス全体何だけど、スムーズなサービスの提供は、円滑なサービスを維持するうえでも必要不可欠なことなんだ。さらに、関連する項目なんだけど、事業性評価融資のことについてふれておこうと思う。
事業性評価融資の新たな方針とは
2014年度9月に、金融庁の金融モニタリング基本方針の中で、事業性評価といった文言が出てきます。この事業性評価とは、金融庁の金融モニタリング基本方針にある通り、金融機関は、財務データや担保・保証に必要以上に依存してはならない。また、借り手企業の事業の内容や、成長可能性などを適切に評価し、融資や助言を行うとされています。このことから、広い意味で融資や支援に対して、定量的情報と組み合わせて活用するものとして考えられています。
かみ砕いていえば、これまでは銀行などの金融機関融資において、担保や保証が前提条件とされていた、リスク管理重視の融資方針でした。当然ですが、経営者側にとって、自宅などの個人資産を銀行に取られてしまうリスクを背負う為、積極的な業績アップにつながりにくかったといえます。
特に銀行などでは、信用保証協会の保証重視の考え方から、信用保証協会から保証が受けられなかった場合、融資を断られてしまうといったケースが常駐化してしまったのです。
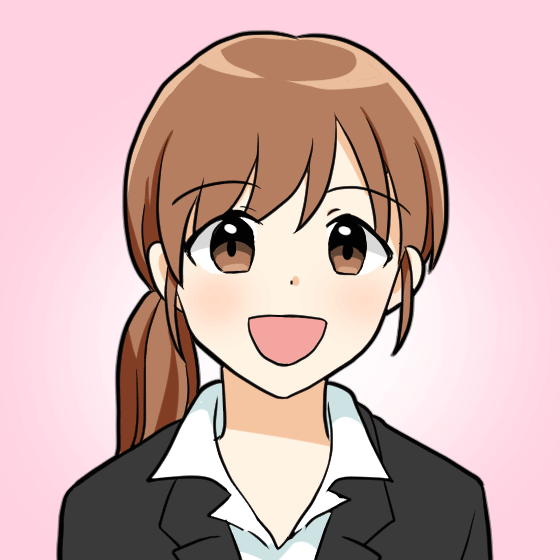
結局は、利用者の与信情報を手早く入手するという事よね。
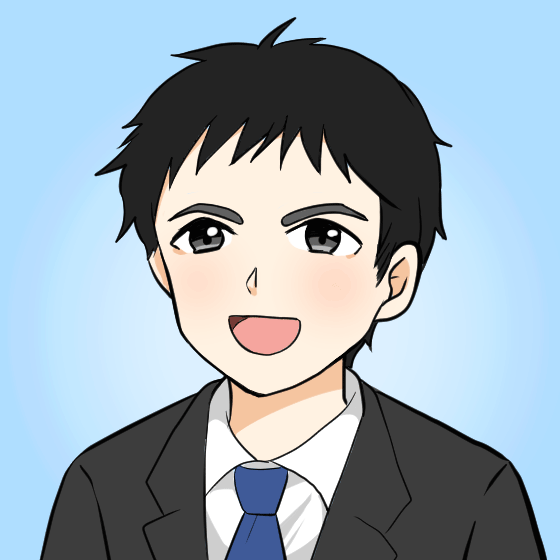
それだけじゃないんだ。利用者の評価が低くても、そのほかの項目が抜けていれば総合的に判断してもらえるというメリットがあるんだよ。
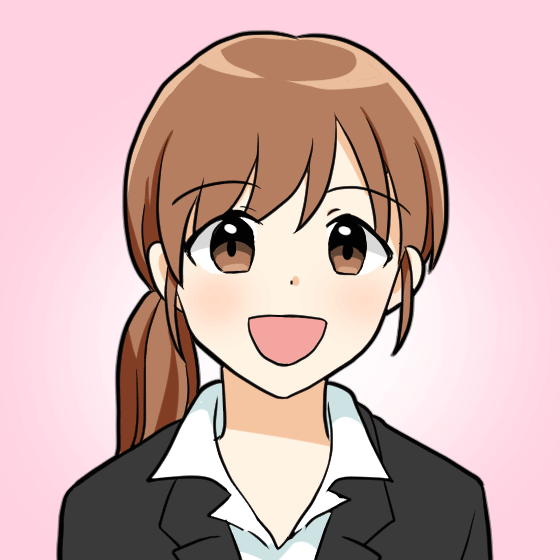
なるほど。これまで簡単に審査にはじかれていた人でも、状況によっては審査に通りやすくなるという訳ね。
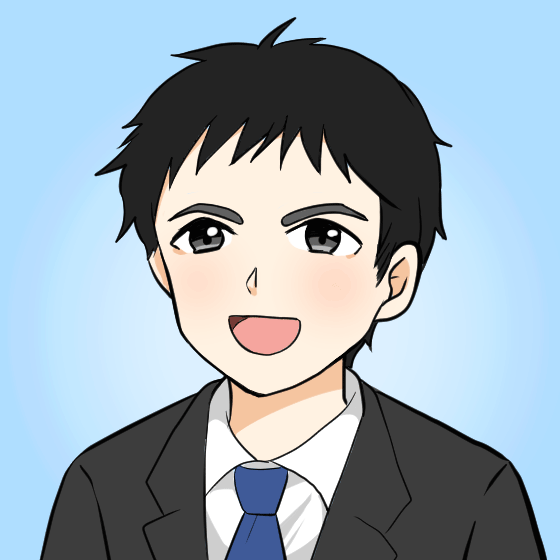
そういうことになるね。貸す側にとっても優良な利用者が増える事はプラスに働くからね。そこで、これまで以上にコンサルティング機能が重要視されるようになったんだ。
コンサルティング機能の重視
これまで、銀行の企業に対する評価基準としては、企業の保有する決算書が重要視されていました。決算書は、いわば企業の過去における実績であり、企業情報の蓄積されたものだったのです。銀行は、この決算書から定量評価を行い、格付けを設定する事により、格付けに基づいた融資を行うというものだったのです。
しかし、金融庁からの金融モニタリング基本方針により、銀行側も新たな考え方を求められるようになったわけです。つまり、これまでの評価基準では、企業の発展性や問題点、あるいは改善点などは重視されず、ただ決算書からの過去の実績値からのみを判断してきました。
金融庁では、新たな金融モニタリング基本方針によって、コンサルティング機能を重視するように求めています。このコンサルティング機能の中で、特に注視しておきたいのが三つほどあります。まず、日常業務や貸付条件の変更時に、企業の経営課題を把握するという点です。
次に、具体的な解決策を提案し、経営改善計画の策定を支援するというものです。そして、継続的なモニタリングや経営相談を通じて、企業自身の主体的な取組みを後押しするといった3点が注目点として挙げられます。
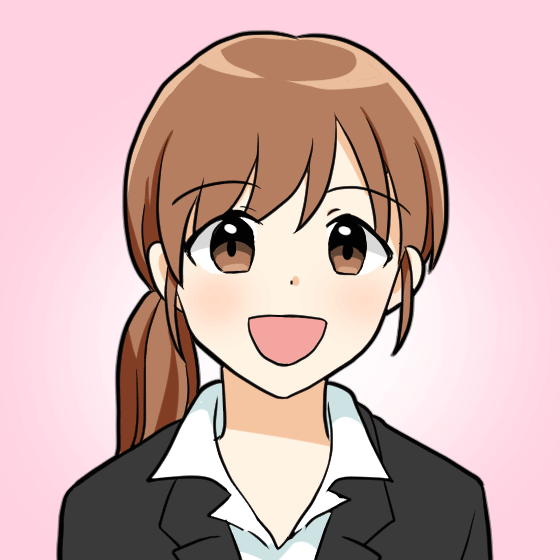
なるほど。優秀な経営者を判断できるという訳ね。
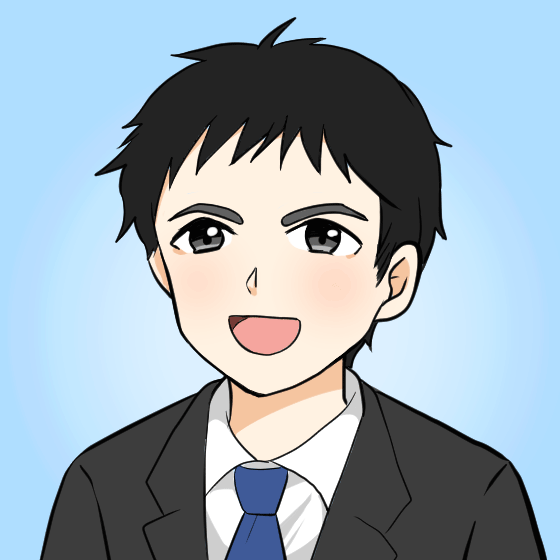
何らかのきっかけで急成長する分野の企業もあるから。そうした意味でも、未来の人材を担うという点でかなり評価できると思うよ。
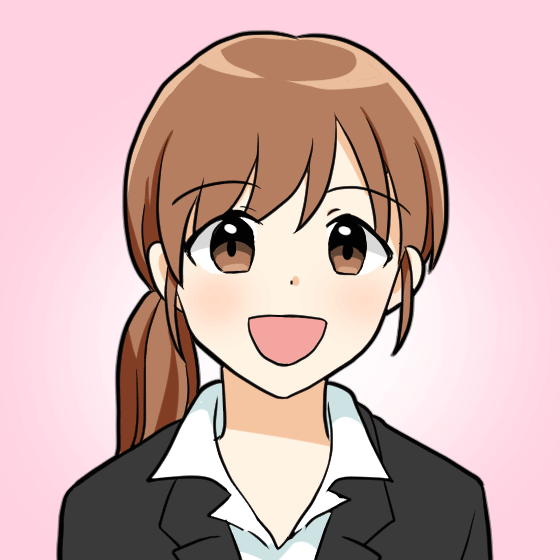
それで、資金調達にも有用に働くんだ。
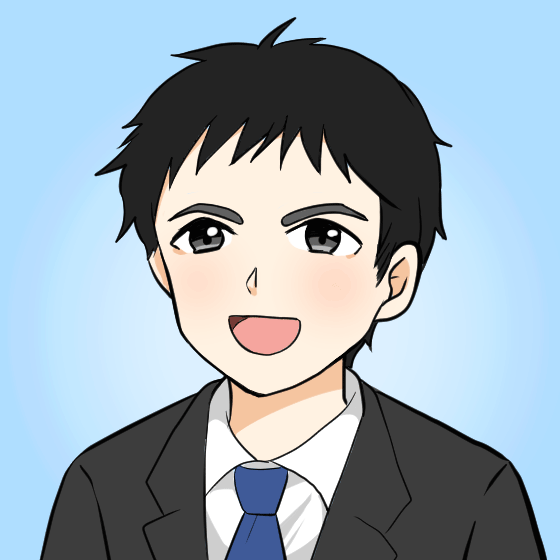
そういうことになるね。
売掛債権を利用した事業性評価融資
これまで金融庁は、ゼロ金利策を含めて、様々なデフレ脱却策を講じてきました。その中で、金融モニタリング基本方針と、2020年に行われる民法の改正は、大いなる期待が寄せられているものです。これまで、売掛債権を利用した融資は存在していましたが、現行の債権法にはいくつかの縛りがあり、自由な資金調達があまりできませんでした。
しかし、2020年の民法の改正の施行により、かなり間口の広がった資金調達が可能になると期待を寄せられています。金融モニタリング基本方針の中で、事業性評価融資は、これまでの融資の考え方をがらりと一変させるもので、事業としての有望さや成長可能性などを評価するというものです。
しかし、実際には、事業としての有望さや成長可能性を評価するというものは、かなり難しいものとしてとらえられています。というのも、事業性の考え方はわかりますが、銀行からしてみれば、それこそ絵にかいた餅でしかなく、どれを指標にしていくかはかなり難しい問題です。
そこで、売掛債権が注目を集める事になります。基本的に、売掛債権は、企業間での取引において実績となるもので、売掛債権の動きを見ることで会社の状況が、つぶさに把握しやすいのが利点です。
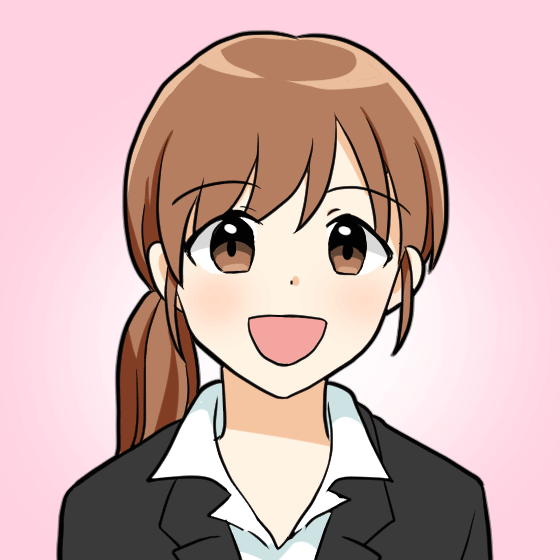
なるほど。モニタリングによって、正当な評価が得られるのはいいことだわ。
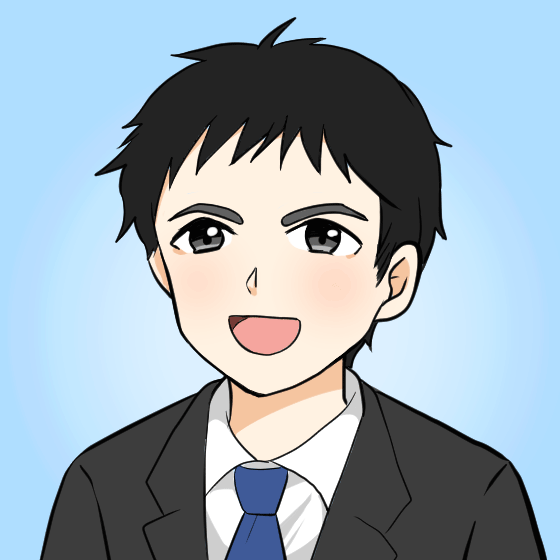
そうだね。そこで今回の法改正により、更なる売掛債権の自由化により、資金調達も楽になることが考えられる。
売掛債権で自由な資金調達
金融庁の政策や、2020年度に施行される民法の改正により、これまでとは一転して債権の自由な資金調達が可能となりました。ファクタリングにおいては、一定の制限こそありますが、債権譲渡禁止特約といった弊害を取り払うことで、自由な売却が可能となります。
また、融資においても、この売掛債権を担保にする融資が自由に行えることになり、資金調達の幅もかなり広がるのではないでしょうか。選択肢としても、融資にすれば、売掛債権の額を超える融資が期待できることになります。
ファクタリングでは、売掛債権の額面以上の売却は不可能ですが、今後将来債権の利用も可能になることを考えれば、これまでよりもいっそう大きな資金調達が、可能となるということを示唆しています。また、モニタリングについても、今後完全自動化が予想されており、審査も比較的楽になることが予想されます。
具体的なモニタリングについては、売上伝票と入金をマッチングさせるということが考えられます。月次で売掛残高を、取引先ごとに管理するようにすれば、売掛金ごとの動きや特徴を入金データとマッチングさせて、モニタリングすることが可能となります。
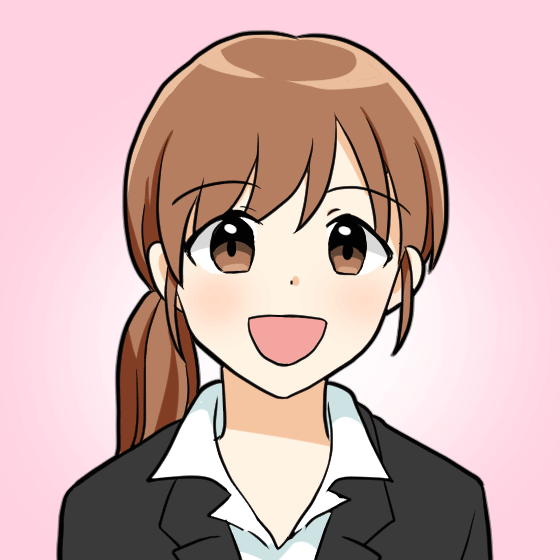
法改正 ! 万々歳だね。
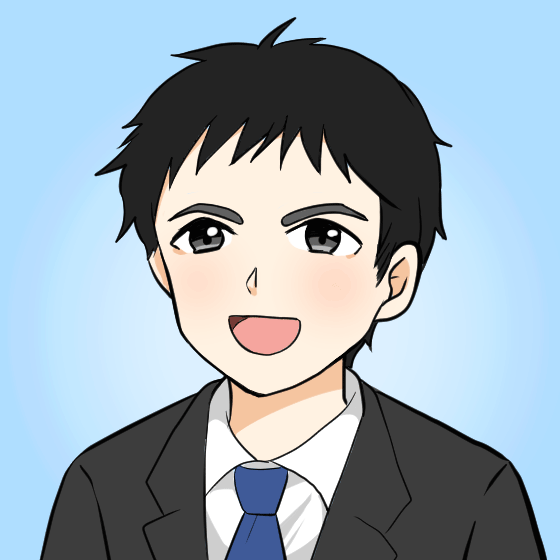
今回の民法の改正は、債権法の改正によって資金調達がよりしやすくなったんだ。
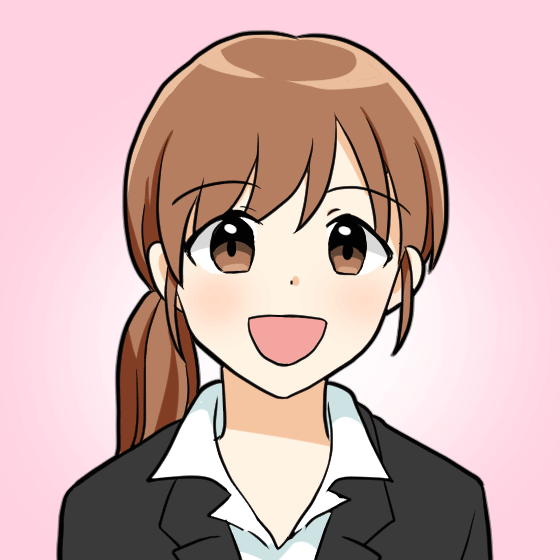
手間も少なくなって、よりスピーディなビジネス展開が望めるわね。
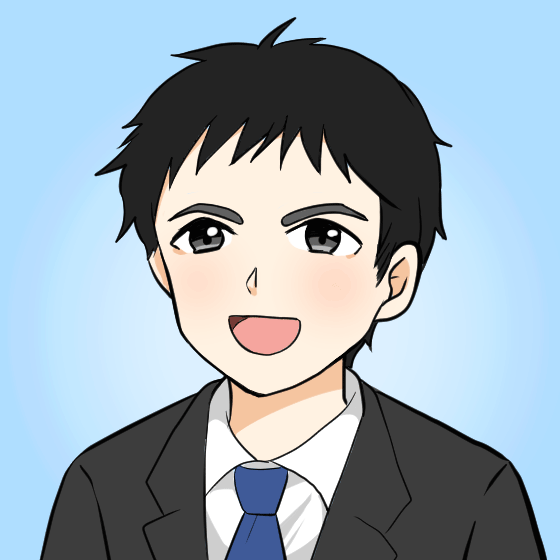
そういうことになるね。
まとめ
長らく続く、国内のデフレ状況ですが、近年では同じデフレ状態でも、景気は上向き傾向にあります。その中で、2020年度より施行される民法の改正により、売掛債権の自由化がさらに推し進められることになります。
これは、企業間だけの話しではなく、個人レベルであっても利用可能になるものと予測されています。

以上、売掛債権評価モニタリングシステムとは ?…でした。
\ メリット盛り沢山 /